カギのことなら「有限会社とまる屋ロックサービス」におまかせください。
カギのことなら「有限会社とまる屋ロックサービス」におまかせください。
災害時に発生する空き巣や窃盗などの二次被害を防ぐ対策

9月1日は、1923年(大正12年)に起こった関東大震災をきっかけとして、1960年(昭和35年)年6月11日の閣議において「防災の日」に制定されています。また立春の日から数えて210日目という台風が来襲すると言われる厄日とも重なり、9月1日を含む一週間を防災週間、当該月は防災月間と定められ、防災が注目される時期でもあります。今回は二次被害をどのように防ぐか、防犯の観点から考えてみましょう。
四季折々の風景、おいしい食事、治安が保たれ、優しさに満ちた人々…。インバウンドの増加でもわかるように、日本という国のすばらしさはもはや語るには及びません。しかし良い面がある一方で、残念な一面もあります。その一つが災害の多さではないでしょうか。
4つのプレートに囲まれた地理的な要因で火山や地震が多く、いつ大きな地震や火山噴火が起こるかわかりませんし、発生しないと断言できる安全な場所はありません。海沿いでは津波や台風による高波のリスクもあります。
また日本だけでなく世界的にも課題になっている、地球温暖化が代表的な環境問題。高温による熱中症の危険、渇水による農業被害、反対に台風は大型化、激甚化しています。さらに通常の低気圧でも線状降水帯があらゆるところで頻繁に発生し、集中豪雨による河川の氾濫、洪水被害など、日常的に異常気象に見舞われています。まさに、日本は災害大国なのです。すばらしい日本に住み続けるには、防災や減災を心がけ、備えをし、一度災害が発生すれば人々で助け合い、被害を最小限に留めようと努力する必要があります。
災害対策で語るべきは、自然による一次被害だけでなく、二次被害です。災害の二次被害というと、大地震にともなう津波・地割れ・液状化現象や、火の不始末による火災、断水・停電などのライフライン遮断などを想像しますが、それだけではありません。じつは被災地では犯罪が横行することがあります。非常時を狙って、犯罪を実行する心無い人がいるのも事実なのです。そのような犯罪が起こらないようにするための抑止的な法整備などと並行して、犯罪を起こさせない個人個人の防犯対策も重要です。
確かに災害発生時は異常な事態です。平常心ではいられないでしょう。身の安全、家族のことを優先するのは当然ですし、その他は目が行き届かないことも当然考えられます。しかし、災害対策のひとつとして、普段からリスクを想定し、準備をすることで、被害を防ぐことも可能です。そのためには、災害時にどのような犯罪が起こりやすく、それらにどのような防犯対策があるのかを検討しておく必要があるでしょう。災害時の防犯対策も、私たちができる災害対策のひとつなのです。
被災した場合、もしくは避難所へ移動した際、直後の生活は自宅と離れた場所になることが少なくありません。すると、自宅は当然空き家の状態となり、住む人も管理する人もいない状況が長く続くことになります。そこにやってくるのが空き巣や窃盗犯。急いで避難した際に持ち出せなかった貴重品や家財道具などが狙われます。
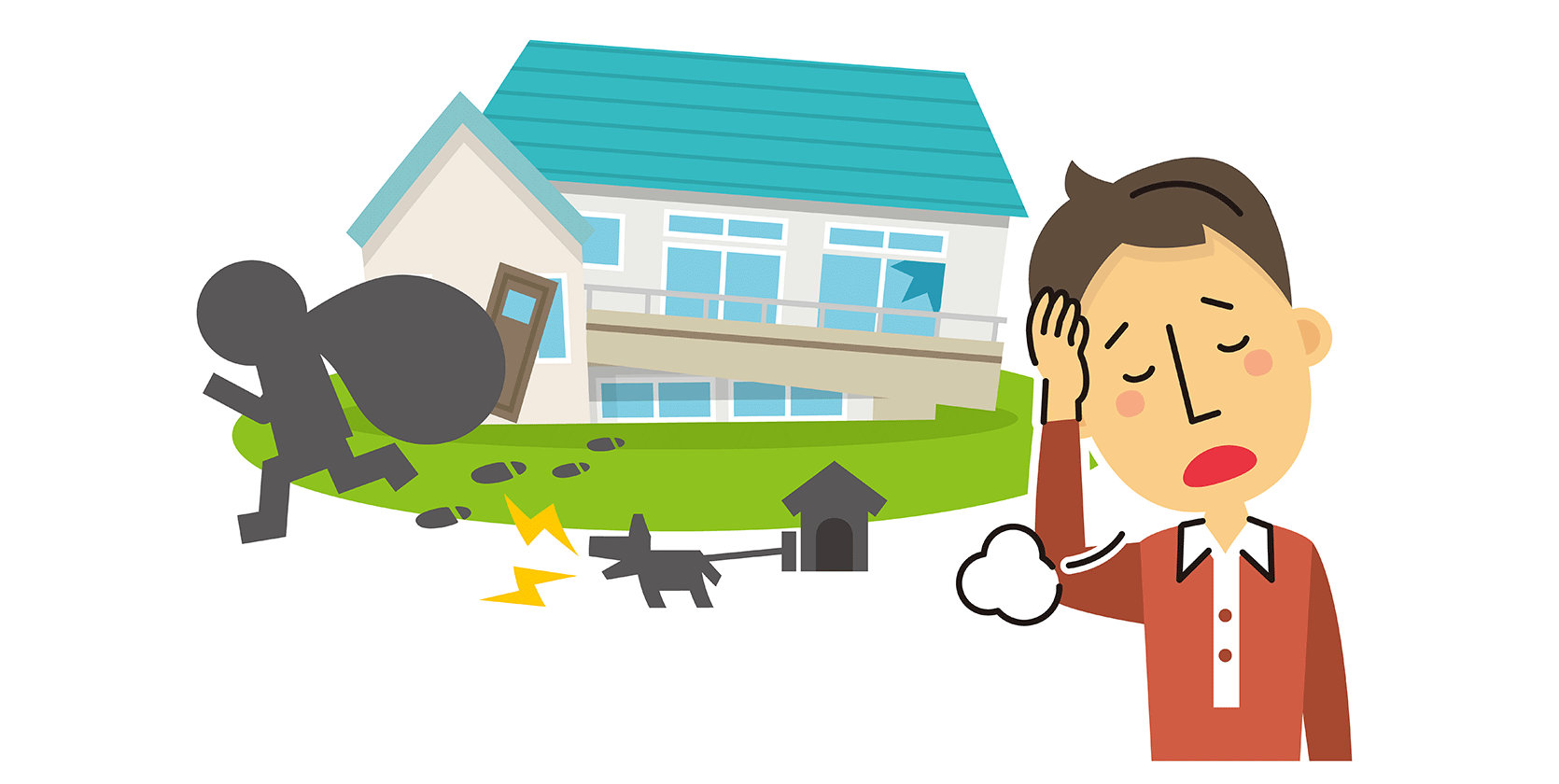
災害は一軒だけが被災するのではなく、周囲一帯が同様の被害が受けることになります。避難は当然、周囲全世帯となりますから、被災地一帯は日中でも人けのない場所、周囲の目が届かない場所になります。そのような場所では性被害、連れ去りなどの犯罪にあう危険もあります。
さらに災害に便乗した、詐欺や悪質リフォームなど悪徳商法の被害なども報告されています。突然の見知らぬ訪問者が電気やガスの点検、家屋の修繕を装って高額な費用を請求されたなどの被害がありました。
ではそれらの犯罪にどのように対策すればよいでしょうか。
ドア枠がゆがんだり、壊れて閉まらない玄関扉や窓は、自分で付けられる補助錠や、南京錠とチェーンなどで厳重にロックをしましょう。内側から付けられる室内補助錠は、避難先や化粧室でのプライバシー確保にも役立つ場合があります。
また、電池タイプの人感センサーライトやブザー、物理的に侵入を抑止する窓用格子などを今のうちに検討しておくことも大切です。

財布やキャッシュカード、身分証などの貴重品は、災害時にも常に身につけておくことが大切です。避難所では多くの人が集まるため、置きっぱなしにしてしまうと紛失や盗難のリスクがあります。特に再発行に手間がかかるものは、失くすと生活に支障が出ることも。
就寝時の対策も考えておきましょう。たとえば、肌身離さず保管できるショルダーバッグを活用したり、リュックにまとめて南京錠やチェーンでロックしておくのも一つの方法です。
自宅を空けるときは、基本的に家族や信頼できる人などに留守番をお願いするのがよいですが、どうしても家を離れる際は、空き巣等に狙われないよう、在宅をアピールしましょう。
割れた窓ガラスが外から見えないように目隠しをしたり、電気が付く場合は付けっぱなしにします。
被災地、避難所など、できるだけ複数人で行動し、とくに女性や子供は一人にならないようにしましょう。子供同士で遊ぶときも保護者が付き添うようにします。トイレにも昼夜問わず大人が付き添いましょう。また死角のあるところには近づかない、外出時は防犯ブザーや電源がなくても使えるホイッスルを持ち歩きましょう。
防災グッズの見直しに併せて、防犯グッズも準備をしておきましょう。とくに、補助錠や南京錠・チェーンロック、防犯ブザーやホイッスルなどは、いざという時に持ち出すものと一緒にしておくのがおすすめです。
その他、家族構成や人数によってもあると便利なものは異なります。事前にプロに相談したり、ショップを訪ねたり、平時から備えておきましょう。